| えほん集 | 「 奥野地区」とは | 参考資料 | Profile etc |
|
|||||||
| 地区「奥野」のページ |
牛久市の奥野地区とは
|
||||
| 生活物資の輸送方法に着目すると面白い。それは生産物の輸送法。農業中心の時代は米輸送、工業発展では部品、都市化すると様々な生活物資となる。 江戸時代は米の輸送が主力で河川を利用した。戦前は工業も商業も発展してきて道路。近代化すると大量物資の輸送となり鉄道に大型トラック。従って自動車道路網や高速道路は発展した。なお多量物資や外国貿易の物資は船による海上輸送である。 鉄道や道路が貧弱な頃は河川が主力で、近辺では小野川は米だけでなく日常生活物資(薪炭等)にの輸送に利用された。坂弘毅氏(つつじヶ丘在)の作成されている資料は多々あるが、牛久と江戸との関係も分かり、お薦めである。 |
||||
| |
| 牛久市のロケーション :都心、水戸から50キロ。成田空港にも近い | |||||||||
| 関東平野のほぼ中央、霞ヶ浦の西南。北:土浦市、西:つくば市、南:龍ケ崎市、東:稲敷市。 牛久市のホームページにその概況。その資料中の5ページに次の左端図等。一見の価値あり。 次図をクリックすると図拡大 また「牛久市の概要」参照
|
|||||||||
 |
 中央を境にして、西側は市街・住宅の人口密集 東は旧奥野村で自然が残り果樹園、牧場もある |
牛久市を構成する3地区の奥野地区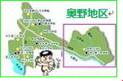 |
 牛久市史から因状+加工 |
||||||
| 牛久市を構成する奥野地区 奥野地区は牛久市の東部(旧奥野村)その面積は市域のおよそ半分。 鉄道は通っていないが圏央道ジャンクションは二箇所ある自然は豊かな一次産業他牧場もある。 西部(旧牛久村・岡田村)は市街をなす牛久地区。明治29年牛久村に鉄道開通、昭和40年以降真っ先に宅地開発をみた。 また。岡田地区は、ひたちの牛久駅開業。多くの宅地が開発され小・中学校も新設。住民増顕著である。 地区住民の統計は、牛久市を構成する3地区と総人口(PDF) にある。 下図はクリックすると拡大 |
||
 |
 牛久市に北側に圏央道が通る 出入口は2箇所 |
 奥野地区(山ゆりの里はこちら) |
| https://www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1435110645_doc_89_0.pdf | ||